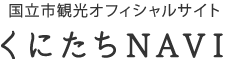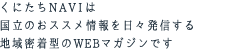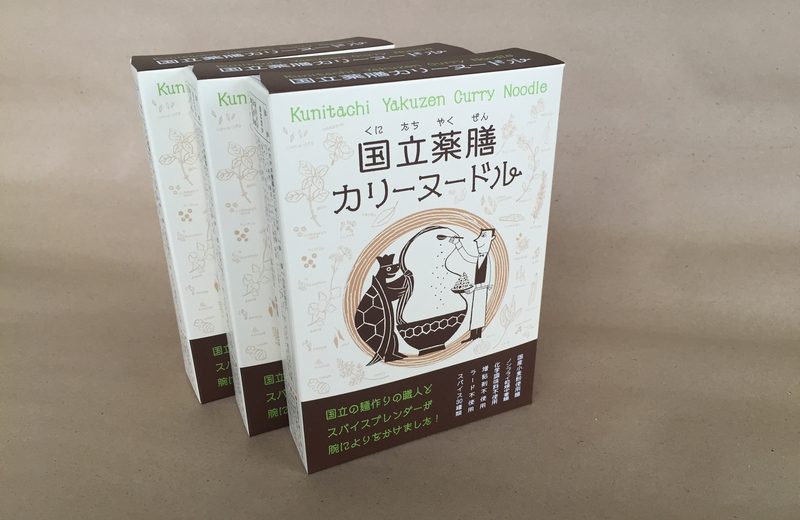立春前日の2月3日夕刻、まだ暗くなりきらないうちから、市内の老若男女が谷保天満宮神楽殿前に、三々五々と集まり始めます。神楽殿では途切れることなく、お囃子が演じられ、集まった人々を楽しませてくれています。
 午後6時になると、拝殿内で節分追儺式(せつぶんついなしき)が斉行され、悪鬼を払い、疫病を除くことを願う神事が始まります。
奉納年男年女が裃姿で並び、宮司による祝詞があげられます。そして、玉串を捧げた後に、豆まきが行われます。
ここまでは神事らしくおごそかな雰囲気の中で、ものごとが進められていきます。けれども、そこはやはり豆まきですから、ちょっぴり愉快なできごとも。
「お宮の中が豆だらけになりましてね・・・もちろん儀式後にはお掃除するのですが、いろんな隙間に入り込んでいて、何かの折にひょっこり出てくることもよくあるんですよ(笑)」(谷保天満宮権禰宜・菊地茂さん)
午後6時になると、拝殿内で節分追儺式(せつぶんついなしき)が斉行され、悪鬼を払い、疫病を除くことを願う神事が始まります。
奉納年男年女が裃姿で並び、宮司による祝詞があげられます。そして、玉串を捧げた後に、豆まきが行われます。
ここまでは神事らしくおごそかな雰囲気の中で、ものごとが進められていきます。けれども、そこはやはり豆まきですから、ちょっぴり愉快なできごとも。
「お宮の中が豆だらけになりましてね・・・もちろん儀式後にはお掃除するのですが、いろんな隙間に入り込んでいて、何かの折にひょっこり出てくることもよくあるんですよ(笑)」(谷保天満宮権禰宜・菊地茂さん)
この追儺式、古くは中国に始まり、日本には7世紀末に伝わって、宮中、社寺、民間でも行われてきました。 宮中の年中行事のひとつで、大晦日の夜に悪鬼を払い疫病を除くために、鬼の扮装をした者を方相氏役が黄金四つ目の仮面をかぶり、玄衣朱襟を着、手に矛と楯を執ったといいます。 古くは大晦日に行われたそうですが、近世、民間では節分の行事となりました。
 追儺式の間中、一般の人々は神楽殿前で、豆まき開始を今か今かと待ち続けます。お囃子を見上げている目の端にうつる空は、刻々と色を深めていきます。
あたりが暗くなって間もなく7時というころ、追儺式が終わっていよいよ神楽殿での豆まきが始まります。
それまで、お囃子を見ながら待っていた人々の心も、期待に高まっていきます。
市内在住の芸能人や有名人、落語家などのまき手が全員裃を身につけ、年男年女に扮して神楽殿に上がります。
落語家による楽しく賑やかな司会で、まき手の紹介や豆やお菓子の奉納者の紹介が行われ、プログラムが進行していきます。
やがてクライマックスの豆まき。
このときばかりは、その場に集う全員が「今年の福」を分けていただこうと夢中で手をのばします。手だけでは足りないとばかりに、袋を広げて受け止める人、まき手の名を呼んで注意を引いて投げてもらおうとする人・・・受け取る側も工夫を凝らします。いただけてもいただけなくても、その顔には笑みが浮かびます。
「福はうち 福はうち」
「鬼はそと 鬼はそと」
おおきなかけ声とともに、数千袋の豆やお菓子が宙に舞い、境内はひととき熱気に包まれます。
谷保天満宮では「福はうち 福はうち」を先に言うのが慣しで、それが特徴なのだそうですよ。
豆まきの儀が終わると、福豆を手に、人々は帰路につきます。
みなさんに福がおとずれますように。
追儺式の間中、一般の人々は神楽殿前で、豆まき開始を今か今かと待ち続けます。お囃子を見上げている目の端にうつる空は、刻々と色を深めていきます。
あたりが暗くなって間もなく7時というころ、追儺式が終わっていよいよ神楽殿での豆まきが始まります。
それまで、お囃子を見ながら待っていた人々の心も、期待に高まっていきます。
市内在住の芸能人や有名人、落語家などのまき手が全員裃を身につけ、年男年女に扮して神楽殿に上がります。
落語家による楽しく賑やかな司会で、まき手の紹介や豆やお菓子の奉納者の紹介が行われ、プログラムが進行していきます。
やがてクライマックスの豆まき。
このときばかりは、その場に集う全員が「今年の福」を分けていただこうと夢中で手をのばします。手だけでは足りないとばかりに、袋を広げて受け止める人、まき手の名を呼んで注意を引いて投げてもらおうとする人・・・受け取る側も工夫を凝らします。いただけてもいただけなくても、その顔には笑みが浮かびます。
「福はうち 福はうち」
「鬼はそと 鬼はそと」
おおきなかけ声とともに、数千袋の豆やお菓子が宙に舞い、境内はひととき熱気に包まれます。
谷保天満宮では「福はうち 福はうち」を先に言うのが慣しで、それが特徴なのだそうですよ。
豆まきの儀が終わると、福豆を手に、人々は帰路につきます。
みなさんに福がおとずれますように。
谷保天満宮 http://www.yabotenmangu.or.jp/
節分祭は18時からです。【取材執筆】小山信子 【取材協力】菊地 茂さん(谷保天満宮 権禰宜) 【写真】くにたち一芸塾写真クラブ、横坂泰介